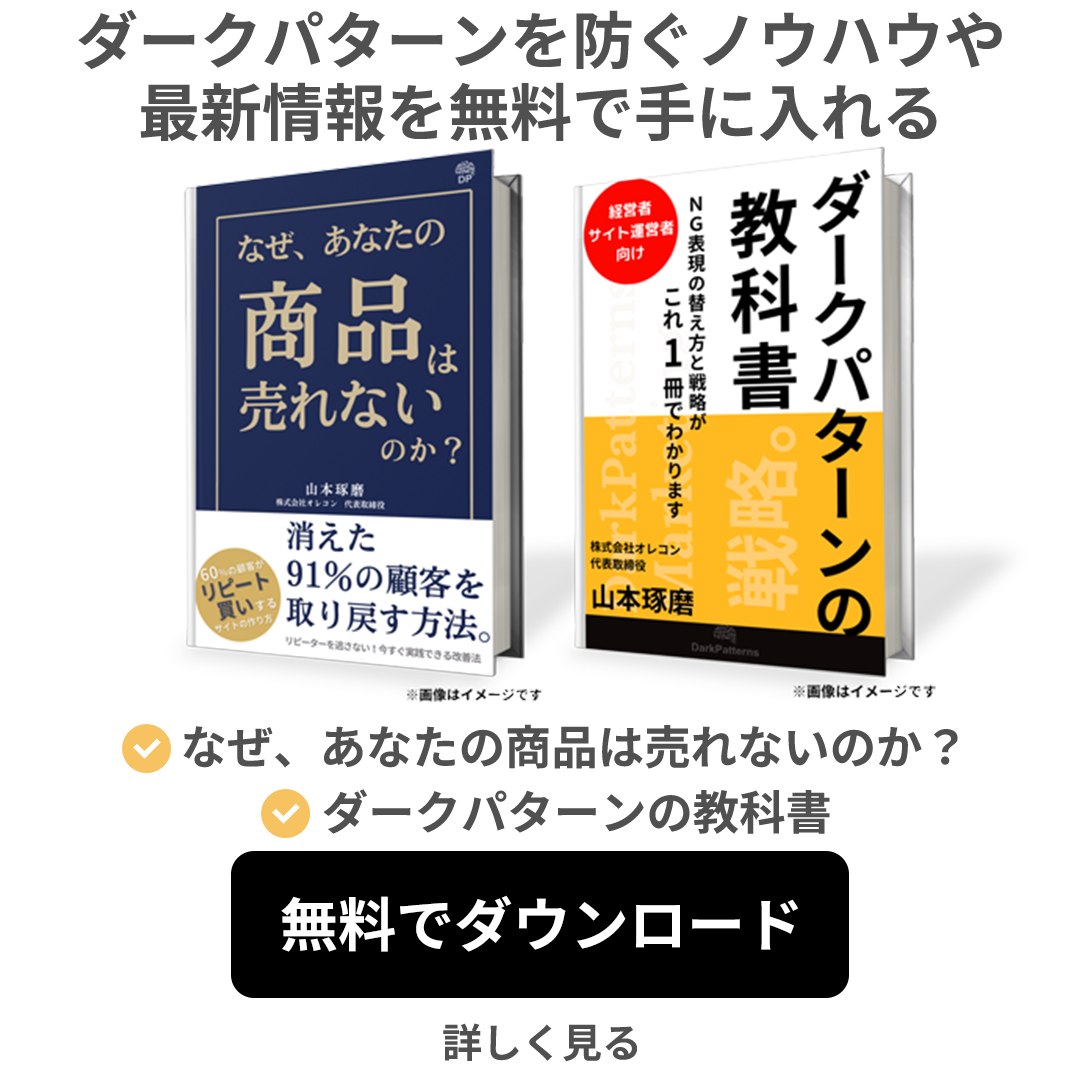定期購入型のオンラインサービスを設計しています。
料金や解約の見せ方によっては、「気づかないうちに課金されていた」といった不満につながるのではと懸念しています。
こうした金銭的な誤認を防ぎ、納得感のある選択を支えるには、どんな設計や配慮が必要でしょうか?
公共サービス系のWeb申し込みフォームを設計しています。
高齢者やデジタルに不慣れな方でも安心して使えるようにしたいのですが、操作に慣れた人向けに最適化しすぎて、意図せず申し込みが完了してしまわないか不安です。
正しく理解して選んでもらうためには、どんな配慮や工夫が必要でしょうか?
ECサービスの改善に関わる中で、「不満はあるけれど問い合わせるほどでもない」UIや導線が、離脱や不信感につながっていないか気になっています。
声に出されにくい違和感に企業が気づき、改善につなげるには、どんな工夫や仕組みが有効なのでしょうか?
健康管理アプリの新機能を設計しています。
継続利用や有料プランへの自然な導線づくりを考える中で、「背中を押す」つもりが押しつけに感じられないか少し不安があります。
ユーザーのためになるナッジと、そうでない誘導を見分けるには、どんな基準や視点があるとよいのでしょうか?
現在、イベントチケット販売サイトの購入フローを設計しています。
購入の終盤になってから初めて手数料などの追加料金が表示される流れは、ユーザーに「思っていたより高い」「最初に知っていれば申し込まなかった」といった不満を与えてしまうことがあるのではないかと思っています。
こうした誤解やストレスを生まないためには、どのような見せ方やタイミングが望ましいのでしょうか?
複数のデジタルサービスに関わる中で、目の前の成果や数字を重視しすぎて、無意識にユーザーを誤認させていないかと不安になることがあります。
ダークパターンを避ける判断を、日々のプロダクトづくりの中でどう組み込んでいけばよいのでしょうか?
ライフスタイル系アプリの導入フローを設計しています。
課金や登録の導線で「どう押してもらうか」に偏りがちで、ユーザーが納得して選んでいるか不安になる場面があります。
必要以上に誘導せず、納得感のあるデザインにするには、どんな点に気をつければよいのでしょうか?
複数のプロダクトに関わる中で、目先の成果ばかりを優先して「本当にユーザーのためか?」と迷う場面があります。
判断が人によってばらつく中で、UX/CXデザイナーが正しさを意識して進めるには、どんな視点や仕組みがあると支えになるのでしょうか?
サブスクリプション型サービスの設計に携わっています。
短期的な誘導よりも、「信頼して使い続けてもらうこと」を重視したいのですが、うまく誘導しすぎると逆に不信感を招くのではと悩んでいます。
信頼を長く保つためには、どんな設計や姿勢が大切なのでしょうか?
定期購入型の健康食品サービスの解約フローを見直しています。
現在は電話でしか手続きできない設計ですが、忙しいユーザーにとっては不便に感じられてしまいますか?
学習アプリの解約フローを設計しています。
「本当によろしいですか?」や「進捗データが消えます」といった引き止めの表示を検討していますが、すでに離脱を決めたユーザーにとって逆効果になることはないでしょうか?
オンライン英会話サービスのマイページを設計しています。
解約ボタンを目立たない階層に置く案がありますが、「どこから解約できるのか分からない」と感じさせることで、不信感を招いてしまうことはないでしょうか?
意図が見えすぎる設計になってしまわないか気になっています。
健康食品のサンプル申込みフォームを設計しています。
フォーム送信と同時に申込みが成立する流れにしていますが、実はその時点で定期購入が始まっている仕様です。
「無料サンプルのつもりだったのに契約になっていた」と感じさせてしまうでしょうか?
定期配送サービスの申込みページを設計しています。
「確認する」などのボタンを押すと即申込みが確定する仕様ですが、見た目からは確認画面に進むだけと誤解されそうで心配です。
ボタンの表示と動作にギャップがあると、ユーザーの信頼を損ねるリスクはないでしょうか?
動画学習サービスの料金プランページを設計しています。
「月額1,200円(年払い換算)」などの表現が多く、月額と年額が混在して比較しにくい構成になっています。
このように料金プランの表記が分かりづらいUIは、透明性を損ねますか?ダークパターンと言われないか心配です。
ファッション系ECアプリの登録フォームを設計しています。
年齢や地域などの個人情報を入力させる構成ですが、利用目的の説明が簡略で目立ちません。
このままでは「何に使われるのか分からない」と不安に思われてしまうのではないでしょうか?プライバシーの観点で問題はないか気になっています。
就職支援サービスの登録画面を設計しています。
会員登録の際、「スカウトや広告配信への情報利用への同意」も利用条件に含めようと思っています。
ただ、サービス本来の利用とは直接関係のない目的に同意が必要となることで、公平性や自己決定の観点から違和感を持たれてしまうでしょうか?
美容系D2Cブランドのキャンペーン申込みフォームを設計しています。
「無料サンプルを申し込む」際に、広告配信や商品案内への同意を必須とする案がありますが、本来の目的に対して情報提供が過剰だと感じられてしまわないでしょうか?
雑貨や日用品を扱うECサイトの購入フローを設計しています。
商品をカートに入れたあと、必ず会員登録が必要になる仕様を検討していますが、「とりあえず買いたいだけ」というユーザーの離脱を招いてしまわないでしょうか?
美容系サブスク商品のトライアル申込みページを設計しています。
初回無料を大きく打ち出す一方で、自動課金の条件はページ下部に小さく記載されている構成になっています。
ただ、「知らないうちに請求された」と感じられてしまうことはないでしょうか?
サプリメント系商品のLPを設計しています。
初回限定の特別価格を大きく打ち出していますが、実際は定期購入が前提であることが目立たない位置にしか記載されていません。
単品購入と誤解され、「知らないうちに定期購入だった」と驚かれてしまうリスクはありますか?
オンライン学習サービスの有料プラン選択画面を設計しています。
3つのプランを並べる中で、初期状態で一番高額な「プレミアムプラン」が選ばれている構成になっています。
機能は充実していますが、納得感や信頼の面で違和感を持たれないでしょうか?
マッチングアプリの登録画面を設計しています。
「利用規約に同意します」のチェックボックスに、あらかじめチェックを入れた状態で表示する案があります。
手間は減りますが、ユーザーが内容を読まずに同意したことになってしまわないでしょうか?
動画配信サービスの登録フローを設計しています。
「初回30日無料」と訴求しつつ、期間終了後は自動で課金が始まる仕組みです。
登録時にカード情報も入力させますが、「気づかないうちに課金された」と感じさせるリスクはないでしょうか?
ライフスタイル系メディアの記事ページを設計しています。
本文中に広告リンクを自然に差し込むネイティブ広告の形式を採用していますが、一見して通常のリンクと区別がつきにくく、「記事の一部」と誤解される恐れはないでしょうか?
美容系サブスクリプションサービスのLPを制作しています。
「モデルの〇〇さんも愛用中」「SNSで話題沸騰中」といった推薦文を載せる案がありますが、明確な使用実績や出典はありません。
こうした根拠のない表現は、ユーザーを誤認させたり、不当表示にあたるリスクはないでしょうか?
アパレル系ECサイトの商品一覧ページを設計しています。
一部の商品に「残りわずか」と表示する案がありますが、実際の在庫とは連動していません。
このUIが誤認を招き、信頼性や法的な面で問題になることはないでしょうか?
期間限定キャンペーンを多く扱うサイトを運営しています。
「今〇人がこのページを見ています」といった表示は、緊急感や人気感を出すために使われますが、本当に効果的なのでしょうか?
アパレル系ECサイトのUIを設計しています。
「残り3時間12分」などのカウントダウンタイマーを常時表示して緊急感を演出する案があります。
こうした設計は、UXとしてどこまで許容されるのでしょうか?
雑貨通販のECサイトを運営しています。
商品の見せ方を工夫する中で、送料や手数料の表示が小さくなったり、目立たない位置になってしまうことがあります。
こうした費用が分かりづらいと、ユーザーに誤解や不信感を与えてしまうのでしょうか?
ファッション系ECサイトの会員登録画面を設計しています。
登録ボタン下に「利用規約に同意します」と表示していますが、文字が小さくコントラストも弱くなっています。
規約への同意が前提となる中で、こうした設計は問題にならないでしょうか?
比較系の情報サイトを運営しています。
ユーザーが「戻る」ボタンを押したとき、本来の前のページではなく広告など別の画面が表示される挙動をさせています。
こうした動きはユーザー体験や信頼性の面で問題になるのでしょうか?
健康診断の予約フォームを設計しています。
検査項目をラジオボタンで提示する際、初期値を入れると内容を読まずに進めてしまうユーザーが出るのではと懸念しています。
こうした場合、初期値は入れない方がよいのでしょうか?
求人応募フォームを改修しています。
志望職種のラジオボタンには初期選択を設けず、ユーザーに自分で選んでもらう設計にしていますが、未選択だとエラーになるためストレスとの声もあります。
初期値なしのラジオボタンは、UXやアクセシビリティの観点で問題があるでしょうか?
サブスクリプションサービスの申込みフォームを設計しています。
すでに初期選択されているラジオボタンに「必須」マークを付けるべきか迷っています。
操作しなくてもそのまま進めますが、「必須」と表示した方がユーザーにとって分かりやすいのでしょうか?
ライフスタイル系メディアのクッキー同意バナーを設計しています。
「OK」ボタンだけを目立たせ、拒否や詳細設定はリンク形式で控えめに表示する案が出ています。
ただ、この設計はユーザーの選択肢をわかりにくくしてしまい、いわゆるダークパターンにあたる可能性がありますか?
カスタムTシャツのオンラインストアを運営しています。
特定のデザインを選ぶと、それに関連する有料オプションを自動でカートに追加する仕組みを検討しています。
ただ、思っていたより高額になったり、「強制されている」と感じて離れていくリスクもありますよね?
SaaSの料金プランページを設計しています。
プレミアムプランの利益率が高いため、その申込ボタンを他より大きく目立たせようかと考えています。
ただ、特定の選択肢を強調すると、ユーザーの判断を誘導してしまい、問題になるでしょうか?
今、動画配信サービスの解約フローを設計しています。
途中で「今だけ50%オフ」などのプロモーションを段階的に表示する案が出ていますが、引き止めが多すぎると「解約しづらい」「押しが強い」と感じられ、逆効果になることはないでしょうか?
SaaS型ツールの解約フローを見直しています。
解約時に「本当に続けますか?」と複数画面で確認したり、引き止めの情報を挟んだりするべきか悩んでいます。
こうした設計は、かえってユーザーの不満を強めてしまう可能性があるでしょうか?
オンラインショッピングサイトの会員登録ページを設計しています。
登録時、メルマガ購読のチェックボックスを初期状態でオンにすれば、多くのユーザーに配信できると考えています。
ただ、その設定が「勝手に登録された」と受け取られ、不快感や即解除につながってしまうでしょうか?