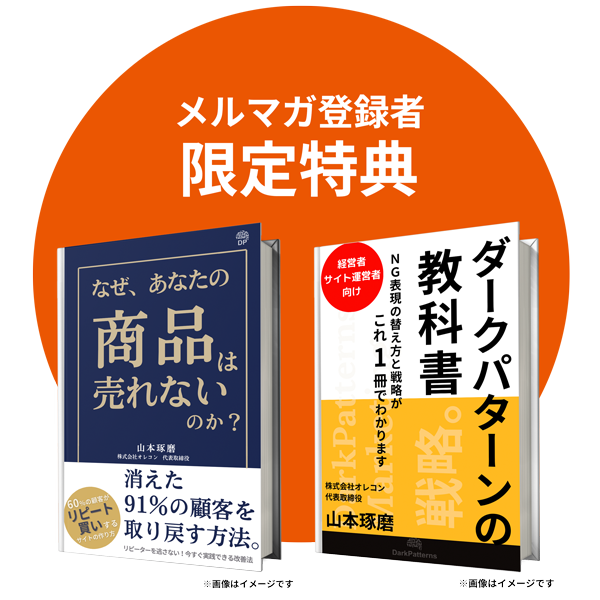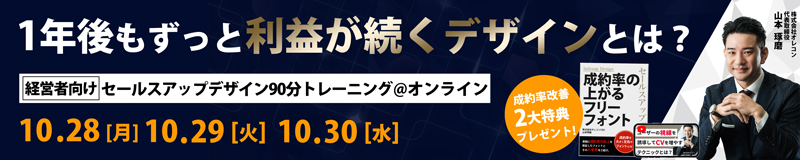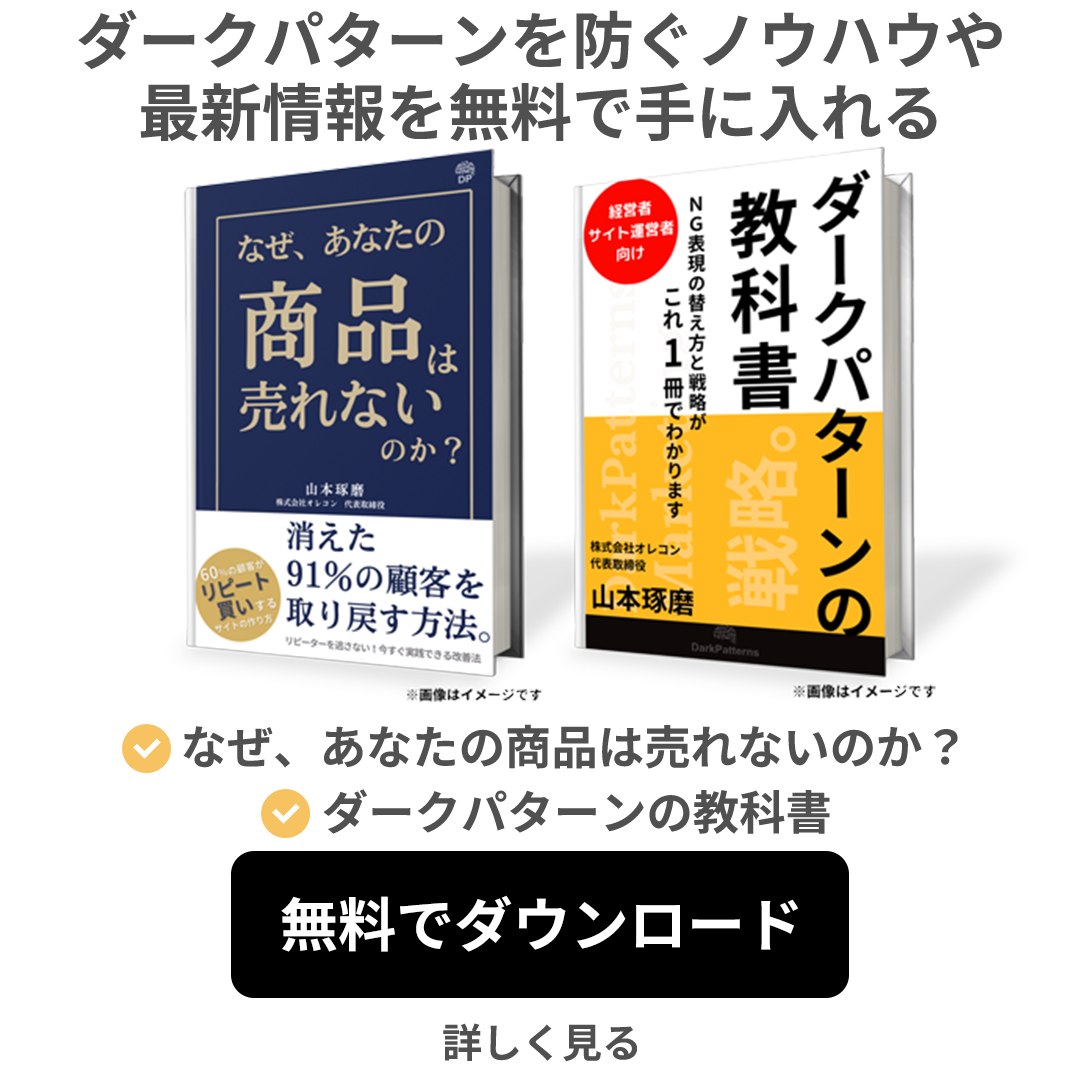アメリカ・ニューヨーク州知事キャシー・ホークル氏は、2025年の州政策発表において、消費者を保護し、市民の財布を守るための新たな法案を提案しました。
この提案は、オンラインショッピングの透明性向上、不公正な手数料の削減、高齢者を狙った詐欺の防止など、多岐にわたります。
この動きは海外での取り組みとして注目されており、日本でも近い将来同様の規制が導入される可能性が高いと考えられます。
以下では、ニューヨーク州の提案内容とその日本への示唆を解説します。
提案のポイント

1. 30日間の返品可能期間の標準化
オンラインショッピングの普及により、返品ポリシーの統一が求められています。
ホークル知事の提案では、一定規模以上の事業者に対し、30日間の返品期間を義務付ける方針が示されました。
ただし、生鮮食品やカスタマイズ商品など特定の商品は対象外です。
この施策は消費者の利便性を高めると同時に、中小企業にとっては返品対応のルール作りが求められます。
日本でもオンラインショッピングの拡大に伴い、同様の基準が求められる日が来るかもしれません。
2. アルゴリズムによる価格差別の規制
消費者の個人データをもとに価格を変更する「アルゴリズム価格設定」が問題視されています。
新たな法案では、企業に対し、価格が個人データに基づいて設定されている場合、その事実を通知することを義務付けます。
また、年齢や性別などの属性データを価格設定に使用することを禁止する方針です。
日本でも個人情報保護が厳格化されつつある中、同様の規制が検討される可能性が高いと言えるでしょう。
3. 過剰な手数料の抑制
低所得者層に特に負担が重い、過剰なオーバードラフト手数料や残高不足手数料に対し、規制が強化されます。
1日に発生する手数料の回数制限や、透明性の高い通知システムの導入が求められる見込みです。
この変更は、金融サービスを提供する中小企業にも影響を及ぼす可能性があります。
日本でも銀行手数料の透明性向上や不当な料金の抑制が求められる時代が訪れるかもしれません。
4. サブスクリプションのキャンセル手続きを簡素化
サブスクリプションサービスの増加に伴い、解約手続きの複雑さが課題となっています。
新たな法案では、解約手続きをサインアップ時と同じくらい簡単かつ明確にすることを企業に義務付けます。
中小企業にとっては、ユーザーフレンドリーな解約プロセスの設計が求められます。
このような動きは、サブスクリプションサービスが増加している日本市場でも採用される可能性があります。
5. “Buy Now, Pay Later”(後払いローン)の規制強化
急成長中の”Buy Now, Pay Later”(BNPL)サービスは、消費者の過剰利用やデータプライバシーのリスクを伴います。
法案では、事業者に対しライセンス取得や監督枠組みへの従属を義務付け、手数料の上限設定や透明性のある契約内容の提示を求めています。
BNPLを提供する中小企業は、事業運営の見直しが必要になるでしょう。
この規制は、日本でも後払いサービスの利用拡大とともに注目される分野です。
6. 高齢者への経済的搾取の防止
高齢者を狙った金融詐欺を防止するため、金融機関に疑わしい取引を停止する権限や、法執行機関への通報義務を与える方針が示されました。
これにより、高齢者が安心して取引を行える環境が整備されます。
高齢化が進む日本でも、類似の取り組みが重要な課題となるでしょう。
ダークパターン最新情報
ユーザーからのクレームや法令違反を招くダークパターンを回避しよう
日本への示唆と中小企業への影響

ニューヨーク州の提案は、消費者保護を目的としたものですが、日本においても同様の規制が将来的に導入される可能性があります。
中小企業にとっては、これらの変化に先駆けて対応策を準備することが重要です。
1. 返品ポリシーの見直し
返品対応のためのコスト管理や業務プロセスの整備が必要です。
2. 価格設定の透明性向上
アルゴリズムやデータ活用に関する規制を遵守し、消費者に公平な価格設定を提供する仕組みを構築してください。
3. サブスクリプションサービスの改善
解約手続きの簡素化や通知システムの改善に取り組むことで、顧客満足度を向上させましょう。
4. 新たな金融規制への対応
BNPLやその他の金融サービスを提供している場合、規制に対応した体制を整えることが求められます。
まとめ
ニューヨーク州の消費者保護法案は、海外での取り組みとして注目されると同時に、日本における将来の規制の方向性を示唆するものです。
中小企業はこれを機会と捉え、信頼を築き、顧客満足度を向上させるための取り組みを進めてください。
規制への適応は初期投資が必要ですが、長期的には事業の成長につながる可能性があります。