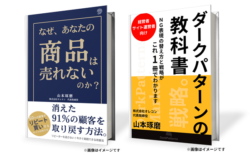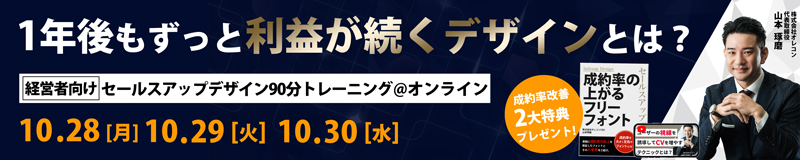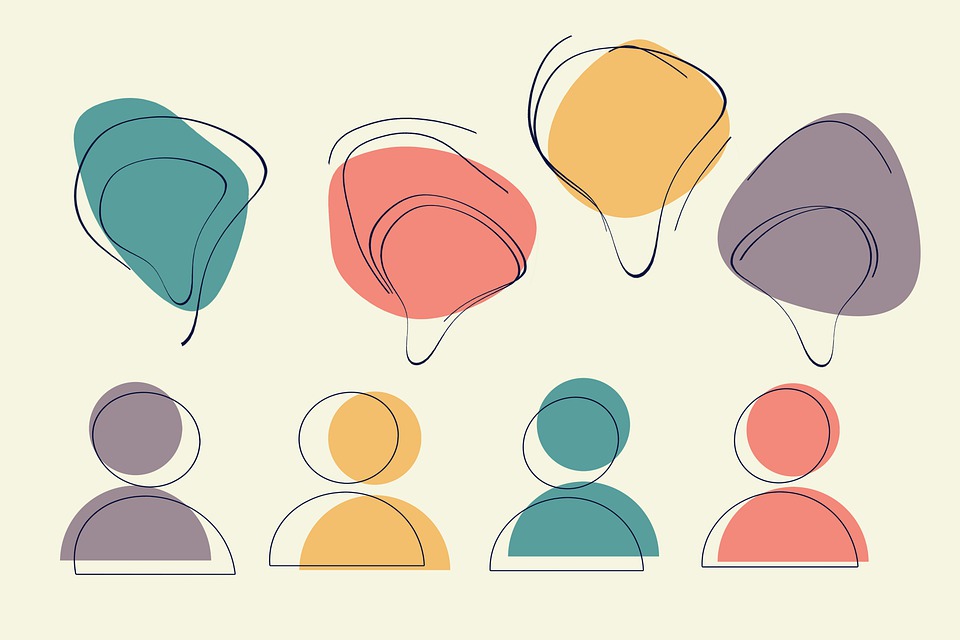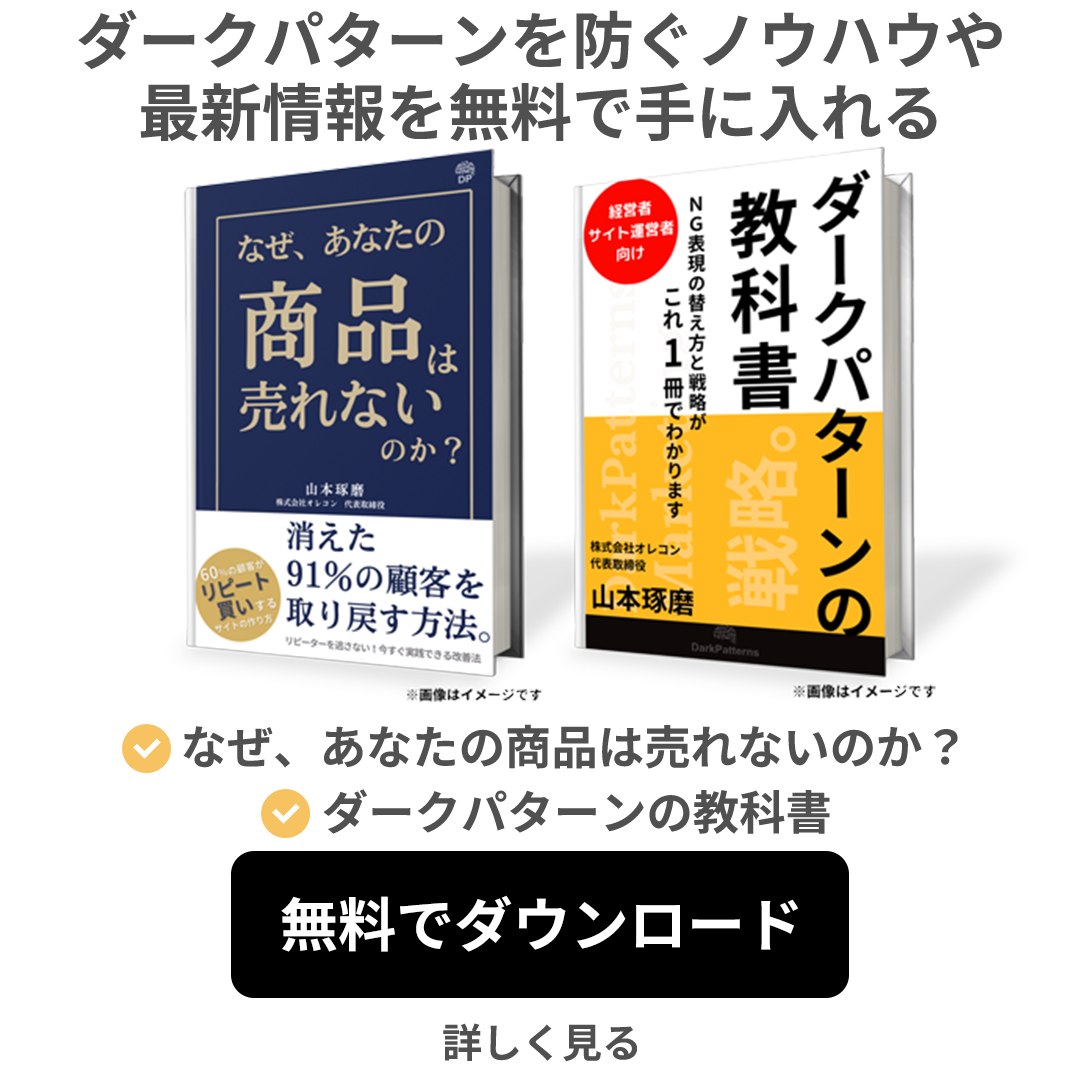Netflixのような現代のストリーミングサービスでは、ユーザーの操作なしに次のエピソードや映画を自動で再生する「自動再生」機能が当たり前になっています。しかし、この便利さは、私たちの時間や意思決定の自由にどのような“隠れたコスト”をもたらしているのでしょうか?
シカゴ大学コンピューターサイエンス学部の研究者たちは、過去の研究をもとに自動再生機能の予期せぬ影響を明らかにし、この一見無害な機能がユーザーの行動や消費パターンにどのように微妙な影響を与えるかを示しました。
この研究は、プレプリントサーバー「arXiv」で公開されており、今年後半に開催予定の「コンピューター支援協同作業・コンピューティング会議(CSCW)」で発表される予定です。研究では、Netflixの自動再生をオフにしたときの影響と、それがユーザーの自律性に与える広範な影響について探っています。自動再生が、私たちとプラットフォームの関係をどう変えているのかについて、説得力ある洞察が得られます。
筆頭著者である博士課程5年のブレナン・シャフナー氏は次のように述べています。「Netflixのようなプラットフォームは、ユーザーが受動的にコンテンツを消費している状態から逸脱しないよう、摩擦をできるだけ少なくするよう設計されています。5秒間の自動再生カウントダウンでは、視聴者がそのプラットフォームを訪れた本来の目的を考え直したり、思い出したりするには、ほとんど時間が足りません。」
自動再生をオフにすると視聴時間が短くなる
この研究では、Netflixを中程度から高頻度で利用していると回答した76人の参加者を対象に調査を行いました。半数は自動再生をオフにし、残りの半数は対照群として、オンのままで視聴を続けた形です。研究チームは、調査期間中および調査開始前の6か月間にわたる両グループの視聴パターンを分析しました。
その結果、自動再生をオフにした参加者は、Netflixの視聴時間が明らかに短縮されました。エピソード間に間ができたことで、何を見るかを振り返ったり、視聴中のコンテンツをより深く考えたりする時間が持てるようになったためです。
Netflixでの1回の視聴セッションあたりの時間は、約18分短縮されていました。これは、視聴を継続するために必要な「摩擦」が増えたことにより、最終的にユーザーが視聴をいつやめるかをより主体的に判断するようになったためと考えられます。
ある参加者は次のように話しています。「何話も見ていたことに気づかされました。以前はあまり意識していませんでした。でも今は、『ああ、これを3回やったってことは、今3話目か』と数えるようになったんです。」
自動再生は、ユーザーがお気に入りのコンテンツに没頭できる便利な機能として広く認識されていますが、今回の研究はその裏にあるリスクにも注目しています。この機能は視聴のハードルを下げ、Netflixの視聴者が途切れることなく見続けられるようにします。しかし、研究者たちは、この「便利さ」が代償を伴う可能性があると指摘しています。たとえば、ユーザーが時間の感覚を失ったり、当初の予定以上に多くのコンテンツを視聴してしまったり、さらには睡眠の乱れや不健康な視聴習慣といった望ましくない行動を助長してしまう可能性があるのです。
ダークパターン
これまでの研究では、自動再生が「ダークパターン」と呼ばれるデザイン手法の一種である可能性が指摘されています。これは、ユーザーの注意を操作し、ユーザーの幸福よりもプラットフォームへの関与を優先するよう仕向けるものです。
「ダークパターンという概念は、ユーザーが自分の利益にかなう意思決定を行う能力を損なう一連のデジタルデザインを指します。」とシャフナー氏は説明しました。「これは一般的に『プラットフォームによる誘導』として、ユーザーを本来選ばなかったであろう行動へと導くものと考えられています。」と続けています。
自動再生をオフにした後、参加者にはその体験を振り返ってもらい、今後また自動再生をオンにするかどうかを尋ねました。結果はさまざまで、約半数の参加者は「便利だから」という理由で再び自動再生をオンにしたいと答えています。「次に見たいコンテンツを再生するためにわざわざ起き上がる必要がない。」という利点を挙げた人もいれば、「ベッドから出なくても次のエピソードに進んでくれるのが気に入っています。」と語る参加者もいました。
一方、約3分の1の参加者は、自分で視聴を続けるかどうかを考える時間が持てたことを理由に、自動再生をオフにしたままにすると答えました。
自動再生の設計と社会的影響への示唆
この調査結果は、Netflixのようなストリーミングプラットフォームが、自動再生機能をどのように設計し、提供するかを見直す必要性を示しています。たとえば、自動再生を初期設定でオフにしたり、アカウント作成時にオン・オフを選べるようにしたりすることで、利便性とユーザーの自律性のバランスを取ることができ、より個人に合った視聴体験を提供できるようになるでしょう。
今後はさらに、次のエピソードが始まるまでのカウントダウン時間を延ばす、あるいは何話まで自動で再生するかを事前に設定できるようにするといった工夫が考えられます。
こうしたデザインの見直しは特に子どもにとって重要です。なぜなら、自動再生には倫理的な問題や法律上の課題があるからです。多くのプラットフォームは、利用者に長く使ってもらうことを重視していますが、その結果、自動再生によってユーザーが自分で「見る・見ない」を選ぶ力が弱まり、知らないうちに判断を左右されてしまう危険があるのです。
実際、米連邦取引委員会(FTC)や欧州連合の一般データ保護規則(GDPR)など、規制当局からの注目も高まっており、ユーザーの行動を意図せず操作してしまうような機能から守る必要性が認識されつつあります。
これには、自動再生やそれに似たデザインによって、ユーザーの健康や自律性にどのような影響があるのかを検討することも含まれます。特に問題視されているのは、子どもが好ましくない使い方をしてしまうようなコンテンツに触れる可能性があることです。なぜなら、自動的に再生される動画は、子ども自身やその保護者が意図的に選んだものではない場合が多いからです。
この研究の上席著者であるマルシニ・チェッティ准教授はこう述べています。「本研究は、注意を引きつけるダークパターンの一つである自動再生が、視聴行動にどのような影響を与えるかを個別に測定した、最初の研究のひとつです。このようにオンライン上の操作的な設計を数値的に評価する研究は今後ますます重要になります。こうした知見が、規制当局やプラットフォーム設計者、研究者たちによるユーザー保護の取り組みを後押しし、社会全体への悪影響を防ぐための手助けになるのです。」
ダークパターン対策方法を無料公開
ユーザーからのクレームや法令違反を招くダークパターンを回避しよう