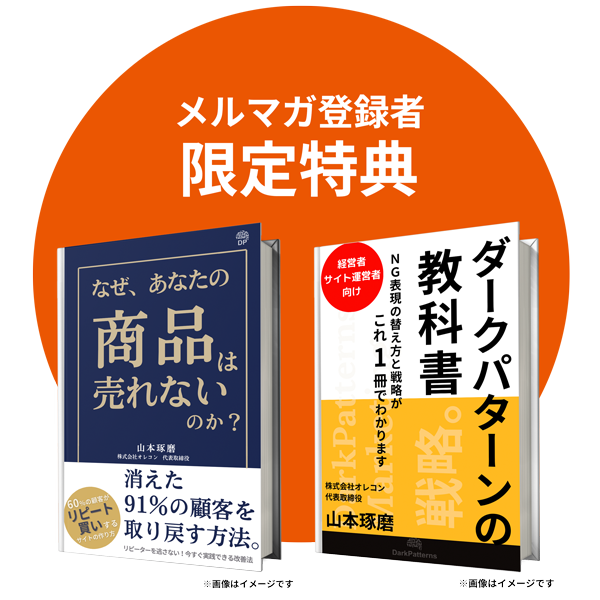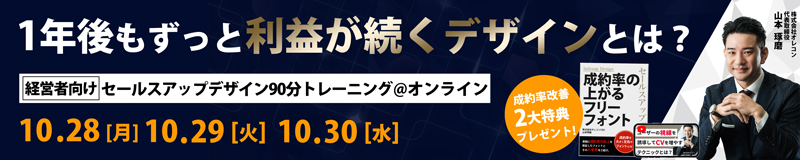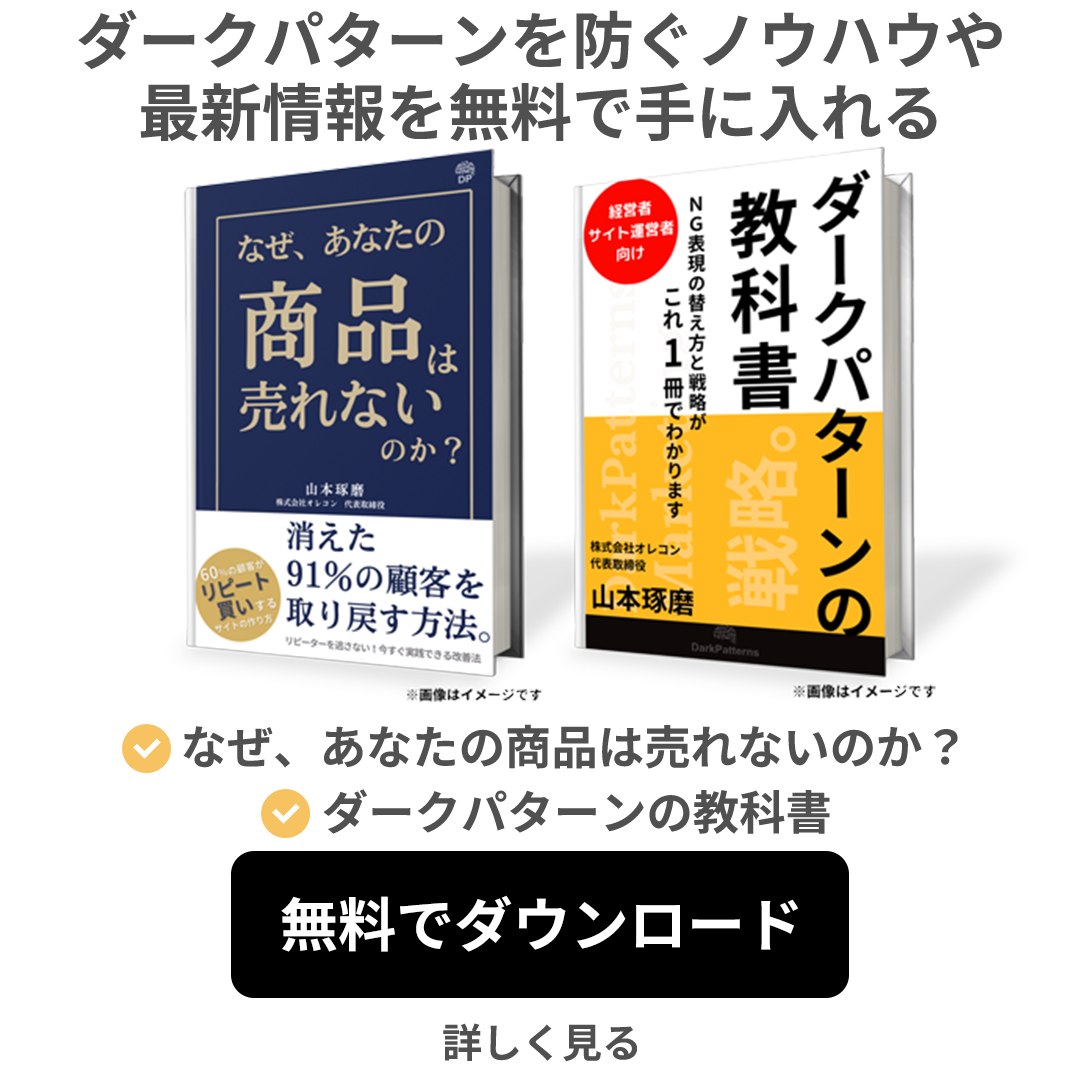「最大〇〇円アップ」「どこよりも高く買取り」といった広告、あなたのビジネスでも使っていませんか?
近年、リユースやサステナブル消費の意識が高まる中、買取サービス市場も大きく成長しています。2023年の市場規模は約1.3兆円に達し、多くの業者が参入する競争が激化しています。
しかし、その一方で、消費者の適切な判断を妨げるような広告表示が問題視され、消費者庁は買取サービスに関する景品表示法の運用基準を改定しました。
これは、消費者が広告に騙されて不利益を被らないようにするための措置です。実際に、消費者庁の調査では「予想より実際の買取価格が低かった」と感じた消費者が約5割にのぼることが報告されています。自社の広告が知らぬ間に規制対象となっていないか、今一度確認が必要です。
消費者庁出典-1024x542.png)
本記事では、買取サービスにおける代表的なダークパターンと、それを避けるための具体的な対策を解説します。
景品表示法改定の背景
令和6年4月に「景品類等の指定の告示の運用基準について」が改定され、買取サービスも景品表示法の規制対象になり得ることが明確化されました。
これは、買取サービスにおける広告が実際の買取価格や条件と大きく異なる場合、消費者に対する誤認を招くリスクが高いためです。
特に、「どこよりも高く買取り」や「何でも買取り」といったキャッチーな表現が実際のサービスと乖離している場合、重大なトラブルにつながる可能性があります。
買取広告に潜む5つのダークパターン
 1. 買取参考価格・買取実績価格
1. 買取参考価格・買取実績価格
一般消費者は、「買取参考価格」と聞くと、その価格で買い取ってもらえると認識しがちです。しかし、実際には、過去の一部の高額な買取事例をもとにした参考価格であり、一般的な取引価格とは異なるケースが多く見られます。
これにより、消費者が予想以上に低い価格でしか買い取ってもらえないと感じることがあります。さらに、買取実績のない価格や、極端に高い過去の一部実績を参考価格として表示する場合は、「有利誤認表示」として景品表示法違反のリスクがあります。
消費者庁の調査でも、「予想より実際の買取価格が低かった」と回答した消費者が約5割にのぼることが明らかになっています。
2. 買取価格アップキャンペーン
「最大20%アップ」や「〇〇円UP」などの表示は、消費者にとって大きな魅力ですが、実際には通常価格と同じか、それ以下の価格で買い取られるケースが問題視されています。
特に、期間限定とされているキャンペーンが常態化している場合や、特定の条件を満たさなければ適用されない場合、景品表示法違反となる可能性があります。さらに、価格アップの対象や条件が曖昧な場合、消費者の期待を裏切る結果になりやすく、信頼を損なう原因となります。
3. 買取価格保証
「最低1万円以上で買取保証」といった表示も一般的ですが、商品の状態や細かな条件が設定されている場合が多く、結果として実際の買取価格が保証額を下回るケースが報告されています。
例えば、汚れや欠品がある場合は保証対象外となることが多く、そのような条件が不明瞭な場合は「有利誤認表示」とみなされる可能性があります。打消し表示が極端に小さかったり、視認性が低い場合も問題となります。
4. 何でも買取り
「どんな状態でも買取可能」といった宣伝も多く見られますが、実際には商品の状態や種類によっては買取不可とされることがあり、消費者が誤解するリスクがあります。
特に、壊れていたり、特定の商品カテゴリが除外されるケースも多いため、注意が必要です。これも「優良誤認表示」として問題視されることがあります。
実際、消費者庁の調査では、「何でも買取り」と表示されていたにもかかわらず、一部の商品は拒否されたとの苦情が多く寄せられています。
5. どこよりも高く買取り
「地域最高値」や「どこよりも高く買取り」という表示は、他社との比較を強調するものですが、実際には調査が不十分である場合、不当表示とみなされる可能性があります。
特に、他社との具体的な比較基準が不明確な場合や、条件付きであってもその条件が明確に示されていない場合、問題となります。
Webサイトに関わる人なら知っておくべき
ダークパターン最新情報
ユーザーからのクレームや法令違反を招くダークパターンを回避しよう
ダークパターンに注意!事業者が今やるべき具体的な対策
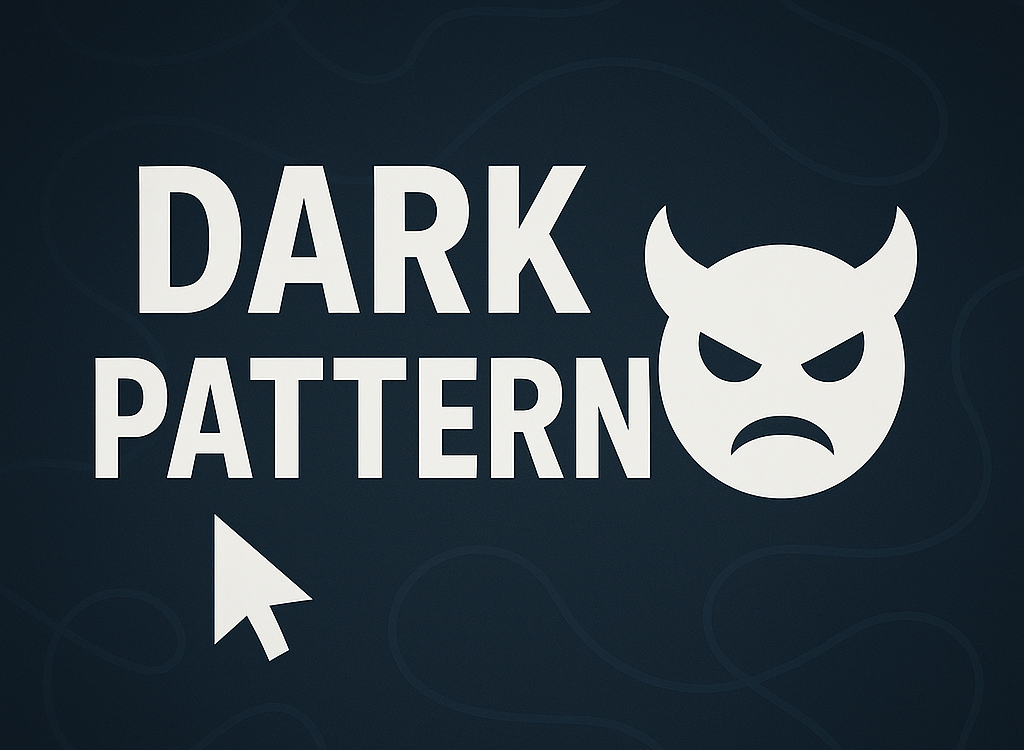
広告表示の見直しを怠るリスクは深刻です。
広告表示の見直しを怠るリスク
-
業務停止や罰金
景品表示法違反が認定されると、消費者庁から業務停止命令や罰金が科される可能性があります。
-
信頼失墜
消費者に対する信頼が低下し、一度失った信用を取り戻すには長い時間がかかります。
- SNSでの炎上リスク
ネガティブな口コミが拡散され、ブランドイメージに大きな打撃を与える可能性があります。
■あわせて読みたい
![]() エステーに措置命令─「うちは関係ない」は危険!表示ミスがダークパターンと見なされる時代へ
エステーに措置命令─「うちは関係ない」は危険!表示ミスがダークパターンと見なされる時代へ
こうしたリスクを避けるために、今すぐ以下の対策に取り組みましょう。
リスク回避のための対策
ステップ1:自社広告のセルフチェック
広告における誤認リスクを定期的に見直しましょう。特に以下のポイントに注意が必要です。
- 広告の位置やサイズ、打消し表示が適切か?
- 実績に基づかない価格表示が含まれていないか?
- 他社比較の根拠が明確か?
■あわせて読みたい⇒![]() 身近に潜む広告に隠されたダークパターン事例10選
身近に潜む広告に隠されたダークパターン事例10選
ステップ2:価格表示の透明化
参考価格や価格保証に関する表示は、実際に取引される価格と一致するように設定し、条件を明示しましょう。具体例や実績がない場合は、控えるのが賢明です。
- 実際の取引価格に基づく価格表示か?
- 例外や条件が明示されているか?
■あわせて読みたい⇒![]() ダークパターン事例 賢い買い物を妨害する「価格比較の阻止」
ダークパターン事例 賢い買い物を妨害する「価格比較の阻止」
ステップ3:キャンペーンの適正管理
常態化している割引キャンペーンや特別価格表示がないかを確認し、適切に期間を区切るようにしましょう。
- 常態化している割引キャンペーンがないか?
- 消費者に誤解を与える表現がないか?
ステップ4:従業員への教育
店舗スタッフが消費者に誤解を与えないよう、景品表示法に関する研修を実施し、適切な対応ができるようにします。
- 景品表示法の基本を理解しているか?
■ダークパターンを回避するノウハウを提供⇒脱ダークパターン企業研修会
ステップ5:法律専門家への相談
表示に関する不安がある場合は、専門家に相談して適切な対策を講じることがリスク回避につながります。
■あなたのサイトのダークパターンを見つけ出し、添削するサービス⇒ダークパターン添削サービス
出典:消費者庁 買取サービスに関する実態調査報告書(PDF)
#ダークパターン #景品表示法 #消費者保護 #買取サービス #消費者庁 #広告表示