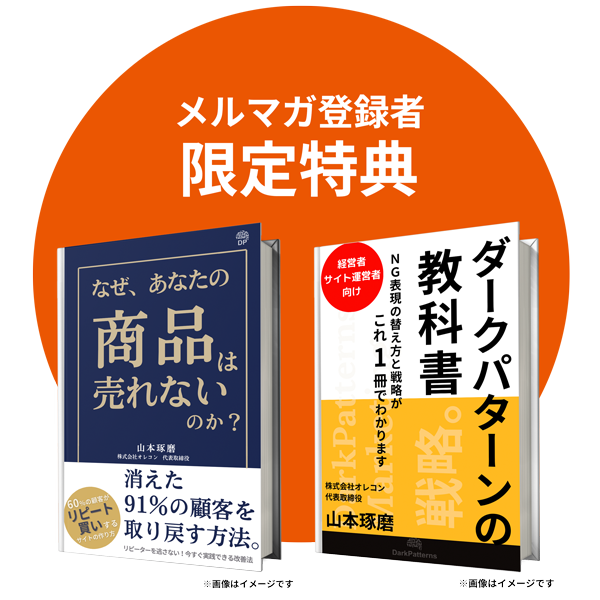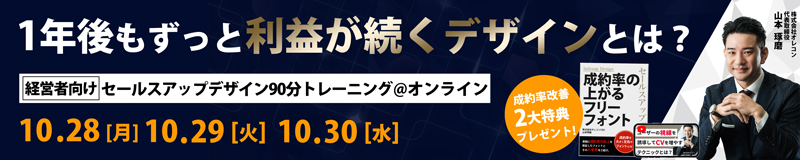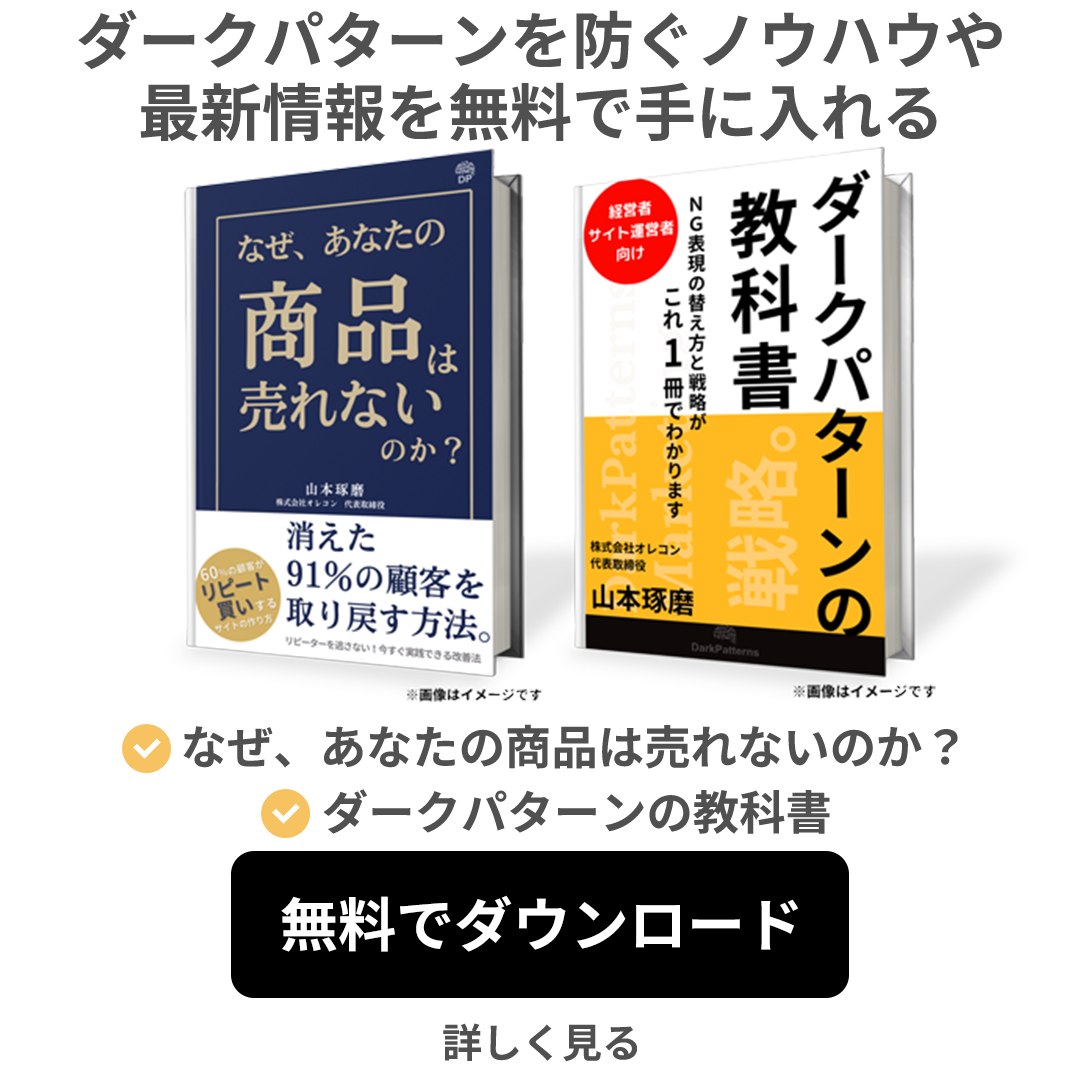2025年1月15日、公正取引委員会(以下、公取委)が、通販サイトやサブスクリプションサービスにおける「ダークパターン」について、独占禁止法を適用して規制可能かどうかの調査研究を開始しました。
消費者の選択を歪め、公正な市場競争を妨げる恐れがあるとして、本格的な検討が行われています。
消費者を惑わす仕組み「ダークパターン」の実態とは?
ダークパターンとは、ウェブサイトやアプリ上で消費者を不当に誘導、強制、操作する仕組みのことです。
例えば、解約手続きを煩雑にする、不要なオプションを無意識のうちに選ばせるようなデザインなどが含まれます。
日本国内では約9,000万人が何らかのダークパターンを経験したとされており、年間被害総額は最大約1.7兆円に達するとの試算があります。
公取委が本格始動、独禁法適用は可能か?
独占禁止法では「不公正な取引方法」として、顧客を欺くような行為を禁止しています。
具体的には、虚偽の情報を表示して利用者を誘導するようなケースがこれに該当します。
しかし、解約手続きを複雑化するなどの手法は、明確に欺瞞とされるケースとは異なるため、現行法で対応が難しい側面も指摘されている状況です。
このような状況を受け、公取委は2025年3月に専門家を招いた国際会議を開催し、最新の国際動向を把握する予定です。
さらに、消費者庁とも連携し、国内外の事例を整理しながら規制の方向性を検討していきます。
ダークパターン最新情報
ユーザーからのクレームや法令違反を招くダークパターンを回避しよう
世界はどう動いているのか? 欧米の先行事例
欧米では既にダークパターンへの対策が進んでいます。
アメリカ:連邦取引委員会(FTC)は2023年、Amazonをダークパターンによって有料サービス「Amazonプライム」に登録させたとして提訴しました。
EU:2022年に成立した「デジタルサービス法」により、消費者を欺くようなサイト設計を禁止しています。
これらの動きは、公取委がダークパターンをどのように規制するかの参考材料となります。
中小企業に求められる対応策とは
ダークパターン規制の強化は、中小企業にとっても影響を及ぼす可能性があります。特に、以下のポイントを見直す必要が出てくるかもしれません。
– ユーザーインターフェース(UI)設計:解約方法やオプション選択を明確かつ簡潔にする。
– 情報の透明性:商品の価格やサービス内容を分かりやすく表示し、誤解を招かないようにする。
これらの対応を怠ると、法律違反と見なされるリスクが高まり、公取委の調査対象となる可能性があります。
注目される新ルールの行方
公取委の調査開始は、日本におけるダークパターン規制の大きな一歩です。
中小企業も、トラブルを未然に防ぐために、自社のウェブサイトやサービス設計を見直し、公正な取引環境を整えることが求められます。
今後、消費者庁や公取委の発表を注視し、必要な対応を早めに行うことが重要です。
参考:読売新聞オンライン:拒否なし選択肢・解約に手間・条件こっそり…通販サイトなどの悪質誘導に独禁法検討、公取委が適用可否を調査