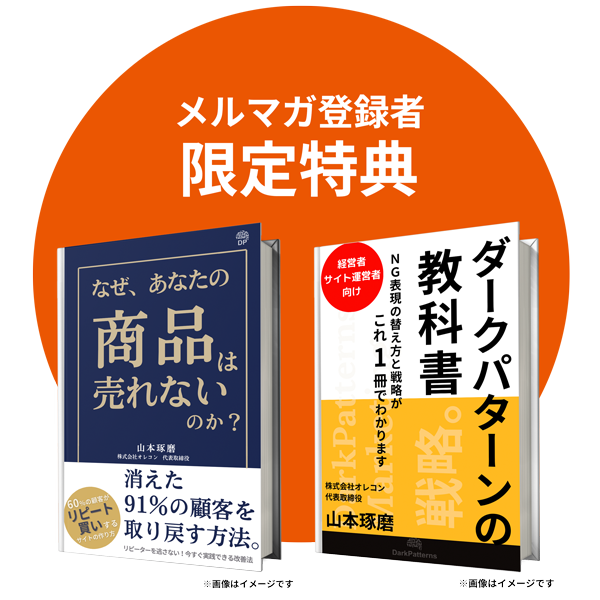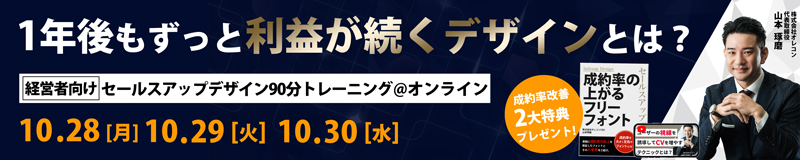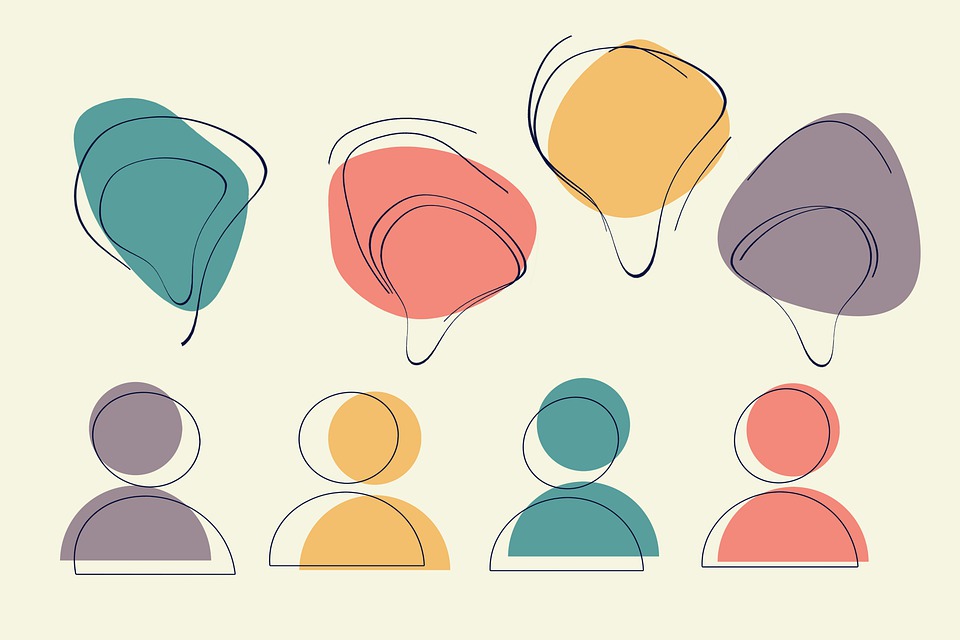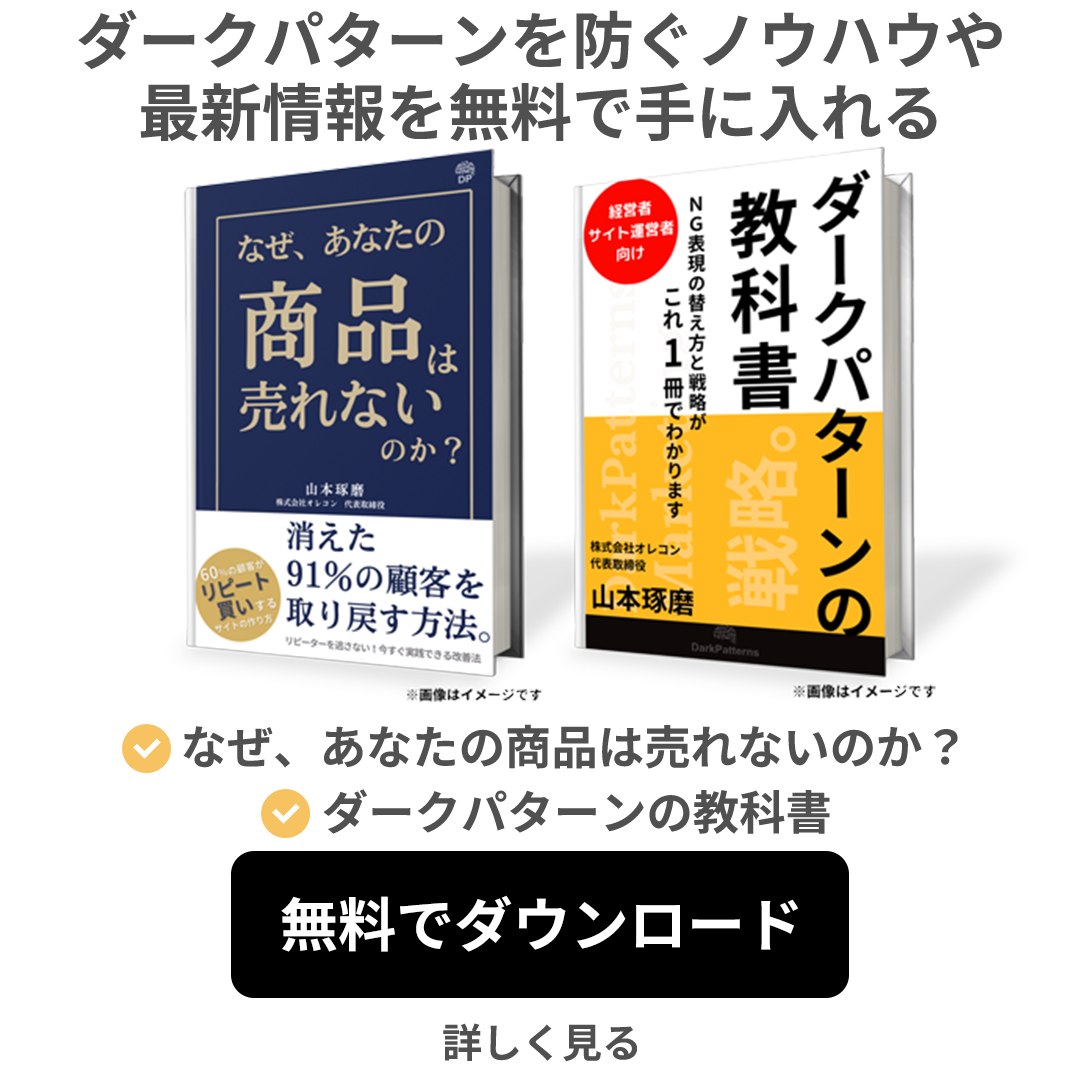2025年4月7日、消費者庁の国際消費者政策研究センターは、ユーザーを意図しない行動に誘導するウェブ上の表示・設計、いわゆる「ダークパターン」に関する実態調査報告を公表しました。
本報告では、国内の消費者が商品やサービスを購入できる102のウェブサイトを対象に、OECDの国際的な分類に基づく調査を実施。意図しない課金、契約、情報提供といったリスクを生むデザインが複数確認され、企業側の対応が求められる状況が明らかになりました。
実際に見つかったダークパターンの傾向とは?
調査の結果、以下のようなダークパターンが多くのサイトで見つかりました。
- 事前選択(Preselection)
例:高額な定期プランが初期状態で選ばれている - 偽りの階層表示(False Hierarchy)
例:「キャンセル」や「拒否」など不利益な選択肢が目立たない位置にある - お客様の声(Testimonials)
例:肯定的なレビューだけを強調し、ネガティブ情報が見えにくい - 強制登録(Forced Registration)
例:購入や問い合わせの際に、必ず会員登録をしなければ進めないように見える

これらの表示は、消費者にとって「気付かぬうちに不利な条件を選んでしまう」設計であり、トラブルの原因になりうると指摘されています。
■あわせて読みたい⇒![]() 知らないと危険!EC事業者のための特定商取引法違反 最新事例と対策
知らないと危険!EC事業者のための特定商取引法違反 最新事例と対策
同じサイトに10種以上の手法が使われるケースも
特に注目されたのは、1つのサイトに10種類以上のダークパターンが組み合わさって使われていたケースが一定数確認された点です。複数のパターンを同時に用いることで、消費者の意思決定がさらに困難になる傾向があるとされ、デザインの設計意図が問われます。
■あわせて読みたい⇒![]() 日本のダークパターン現状、意識調査から分かる企業に求められる対策
日本のダークパターン現状、意識調査から分かる企業に求められる対策
調査対象には中小企業サイトも
調査対象には、大手通販サイトだけでなく、消費者相談が寄せられた中小規模のECサイトも含まれていました。
たとえば次のような事例が報告されています:
- 「初回550円」の表示だけが強調され、2回目以降は自動的に高額な定期購入に移行する
- 解約方法が目立たず、事実上困難になっている
- クーポン条件が小さく表示され、実質的には使えない構成
こうした設計が「意図的」であるか否かにかかわらず、消費者庁は改善の必要性があると判断しています。
ダークパターン最新情報
ユーザーからのクレームや法令違反を招くダークパターンを回避しよう
景品表示法・特商法に違反するおそれ
報告書では、以下のような日本の法制度との関連性にも言及されています。
- 景品表示法
→「優良誤認表示」や「有利誤認表示」に該当する可能性(例:定期購入を明記せず価格のみ強調) - 特定商取引法
→ 購入確認画面での「特定申込み」に必要な表示が不十分なケース - 個人情報保護法、特定電子メール法
→ クッキー同意の強制や、メール配信の解除が困難な設計など
特に「みなし同意」など、現行法上は即違法とされない設計についても、消費者の利益保護の観点から今後検討の余地があると指摘されています。
■あわせて読みたい
![]() 大正製薬が景品表示法違反で措置命令!ステマ規制違反事例から学ぶ
大正製薬が景品表示法違反で措置命令!ステマ規制違反事例から学ぶ
![]() 夢グループに6,589万円の課徴金命令 「期間限定価格」で景品表示法違反と認定
夢グループに6,589万円の課徴金命令 「期間限定価格」で景品表示法違反と認定
![]() 【東京都が初の措置命令】SNS広告で「誰でも痩せる」 ステルスマーケティングが景品表示法違反に
【東京都が初の措置命令】SNS広告で「誰でも痩せる」 ステルスマーケティングが景品表示法違反に
今後、企業が取るべき対策とは?

調査では、単なる違反の摘発にとどまらず、基準の標準化や実証実験の必要性といった提言もなされています。
中小企業が取るべき対応として、以下の3点が挙げられます。
- 購入・登録・解約フローの再確認
→ 意図しない選択を誘導していないか点検しましょう - ユーザー目線でのデザイン評価
→ 社外の人にも試してもらい、誤解を招くポイントがないかチェック - 社内ルールやガイドラインの整備
→ デザイナーやマーケティング担当者への周知も重要です
ユーザーに寄り添う表示が、信頼と売上を生む時代へ
ダークパターンは短期的に売上を上げられる場合もありますが、消費者との信頼関係を損ない、ブランドイメージの毀損や法的リスクを引き起こす恐れがあります。
逆に言えば、わかりやすく誠実な表示は、今後の差別化ポイントにもなります。事業規模にかかわらず、今こそ「安心して使ってもらえるサイト設計」への見直しが求められています。
■対策を知る⇒![]() 国民生活センター調査発表|ダークパターン相談の増加と企業が取るべき対策
国民生活センター調査発表|ダークパターン相談の増加と企業が取るべき対策
■あなたのサイトのダークパターンを見つけ出し、添削するサービス⇒![]() ダークパターン添削サービス
ダークパターン添削サービス